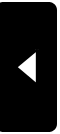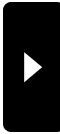会社の存在意義

ただ単に長く存続さえすれば良いというものでもない
地域社会や社員にどう良い影響を与え続けられるか
たとえ短命に終わっても
地域社会にどんな存在した証を残せるか
社員が、会社で得たスキル・人間的成長を持って次のステージへ進めるか
これも立派な社会貢献
みなさん、こんにちは。
今日は、KJ法という文化人類学者の川喜田二郎さん(東京工業大学名誉教授)がデータをまとめるために考案した手法で私達がやりたい事、求められると思われる事、できそうな事を考えました。
アイデアを出すのは思った以上に大変です。みんなで力を合わせて頑張っています!

みなさんはどんな日となりましたか。
明日は金曜日です(^^)/
今週も残り少ないですが、楽しみます!
今日は、KJ法という文化人類学者の川喜田二郎さん(東京工業大学名誉教授)がデータをまとめるために考案した手法で私達がやりたい事、求められると思われる事、できそうな事を考えました。
アイデアを出すのは思った以上に大変です。みんなで力を合わせて頑張っています!

みなさんはどんな日となりましたか。
明日は金曜日です(^^)/
今週も残り少ないですが、楽しみます!
今日は暖かい日となりましたね!
みんなで試行錯誤しながら、仕事の内容を考えています。\(^o^)/

Have a great day,everyone!!!
みんなで試行錯誤しながら、仕事の内容を考えています。\(^o^)/

Have a great day,everyone!!!
ナースステーションおきなわ始動開始!
お天気も良く、気持ちいい春の日を感じます。
ナースステーションおきなわの幸先いいスタート
に期待は膨らみワクワクしま~す(*^ー^)ノ
お天気も良く、気持ちいい春の日を感じます。
ナースステーションおきなわの幸先いいスタート
に期待は膨らみワクワクしま~す(*^ー^)ノ


大人の付き合い方
ギブアンドテイク、ウィンウィン、お互いが高めあい利する付き合いが基本
物・心、何を与え、得られるか
一見、無償の行為に見えても、満足感、ノウハウ、人間的成長を得るというパターンもある
恋愛もビジネスも一緒

ワンマン経営の長所
① 意志決定の速さ
② 責任の所在が明確
③ 足の引っ張り合いがない
欠点
① 加齢による肉体的、思考的衰えが経営全体に影響をあたえる
② 経営が悪い方向性に向かった場合、修正しにくい
③ 思考する、判断する、決断する人材が育たない
ワンマン型経営の長所を取り入れ、欠点を排除した総合的経営を目指す

感謝、感謝、感謝あるのみ
今、私を支えてくださっている方々に感謝
過去に助けていただいた方々に感謝
健康な体に感謝
過去に私を攻撃し苦難を与えた方々にも感謝
人間というものを学ばせてもらい、反面教師になってもらった
過去の苦労にも感謝
多くを学び、乗り越える力と自信を得ることできた
今の苦難にも感謝
のっぺりじゃない、エキサイティングな人生を歩ませてもらっている
感謝、感謝、感謝あるのみ

ミスをほめる?!
正確には、ミスを報告したことをほめる
人には防衛本能がある
叱られて落ち込む、立場が悪くなる、外される、そんな危機を回避しようとする
それでも、ミスを報告する
ミスは、チャレンジ・行動の結果
ミス・失敗事例は大事な情報
そんな大事な情報を提供してくれたことをほめてあげよう

事業行動指針
①社会的ニーズを徹底的に探り、私たちのスキルを駆使して応えていく
②事業理念・目的に沿っているか
②法令順守
③お客様とサービス提供側の安全確保(身体的・社会的)
④チャレンジ!!まずは行動!!但し無謀はしない(段階を踏んで、深く掘り下げ拡げていく)
ちょっと寒い中、海辺をお散歩です。

ブラック企業なんてアリ?
商売人が、大事な自分の商品を乱暴に扱ったり、ぶっ壊して捨ててしまうことなんてあり得るのか
そんな商売あっというまに潰れてしまう
社員は、会社の財産であり、商品
常に品質の向上(スキル・モチベーションのアップ)と安定供給(雇用の安定化)を図らなければ、商売にならない
しっかり良い商品作りに励まねば
俗に言うブラック企業と呼ばれる連中は、自分で自分の首を絞めている
と、偉そうにのたまっているが
そっち側の人間にならないように、しっかりしなければ・・・

訪問看護ステーション事業部門
ソーシャルワークナース事業部門と連携を取りながら相乗効果を図り、
(人員の横断的活用、営業パイプの共通化・効率化等)
一般的・ビジネスモデルの確立した高齢者対象を中心としたサービスを当初は進めていき、
小児を対象としたスキルの向上を図り、経験を積みながら、
徐々に小児対象の比率を高めていき小児特化型訪問看護ステーションへと移行していく。
サービスを提供するご高齢の方々は、人生の大先輩であり、激動の沖縄を生き抜き、現在われわれが平和で豊かな社会の恩恵を受けている礎を築いていただいた方々です。
尊敬と感謝の念を持ち、この職務を通して恩返しをしていかなければならない。

事業展開・行動計画
事業理念、「三つの宝」に則り進めていく
≪理念≫
「三つの宝」
1.子は世の宝
・子どもたちとその家族の、平穏な暮らしと明るい未来づくりに看護サービスを通して貢献していきます。
2.安心・健康は地域の宝
・看護師を有効な社会資源と位置づけ・活用し、地域の安心・健康なまちづくりに貢献します。
3.看護師は医療・福祉業界の宝
・地域の看護師が常に学び成長し自信と誇りをもって安心して職務に当たれる社会的環境づくりに貢献します。
≪ビジネス行動指針≫
看護師を、サービス商材としてとらえ、商品開発・販路開拓(既存の医療施設・医療保険・行政施策ではカバーできないニーズに応える)、高品質化(看護スキル・モチベーションの向上)、安定活用(福利厚生・待遇の向上)に取り組んでいく。
≪具体的ビジネス展開≫
●訪問看護ステーション事業
・既存の、訪問看護ステーションの開設・運営ノウハウを活用し事業展開していく。
・当初は、ノウハウの確立した一般的な高齢者対応を中心にした事業を行いながら、小児対応特有のスキル・ノウハウを身に着けていき、事業理念に則った小児特化型訪問看護ステーションへと移行していく
●ソーシャルワークナース事業
・ツアー・イベントナース
・ワンコイン簡易血液検査・健康相談サービス
・ナースの便利屋さん
・企業訪問健康チェック・相談サービス
・看護師向けビジネススクール
・看護師向け婚活サポート
等々
※ 多岐にわたる業種・業態へ、看護師の活躍の場を創造・開拓していく
※ 両事業への人財の横断的活用や、関連する人脈・パイプづくり、情報収集など営業活動の相乗効果を図り、優先順位・スケジューリング、資金投入計画に留意しながら事業展開していく。
事業展開への心得
・理念追求は「頑固」に、それに向けた手段は「柔軟」に
・「人」がすべてのこの事業、人の偉大さ、素晴らしさ、強さ、恐ろしさ、愚かさ、弱さを受け入れ消化していく
・すべての人には、長所・短所、得意・不得意、明と暗がある、パズルのようにうまく組み合わせていき、一つの力を作り上げていく
・お金は追っかけると逃げていく、社会に認められ、求められ、満足を提供できれば必ずお金は後からついてきてくれる
・ギブアンドテイクの徹底した、お互いが高めあい利する人間関係を構築し、利己主義に走らない。
・成功事例を参考にするのも大事だが、失敗事例の逆をするという発想も取り入れていく
・我以外皆我師(相手がたとえ子供であっても、物であっても自分以外の者すべてが、学ぶことのできる先生である)
等々

看護師さん面接にいらっしゃいました
●近所のバーガーショップでお会いしました
※部屋で二人っきりでは不安でしょうから、外で会うことにしました
↓
●名刺を渡して自己紹介
※これまで、多くの企業採用面接を受けた経験があるが、ほとんどの面接担当者は自分の名前を名乗らなかった
採用面接という人と人との出会いの場、お互い自己紹介するのは、子供でも分かる当たり前の理屈
↓
●お互い履歴書を交換して個人レベルの自己紹介しあう
※採用面接は、情報交換の場でもある、相手の人物像、考え方、生活状況などの情報を得るのと同じように、こちらの情報も提供する
↓
●会社の経営理念・目標、これからのスケジュール、現状を説明
※いざ採用後に、初めて知った、こんなはずではなかった、は無いようにしたい
↓
●「聞きたいこと・知りたいことをどんどん聞いてください」質問に答える形で話を進めていく
※好奇心、積極性、知りたいことを聞き出すスキルも見てみたい
↓
●終了
●お互い検討して、1週間後に結論を出す
※お互いメールアドレスを交換して、その間、追加の質問等やり取りをしてお互いのマッチングの可能性をさぐる
※採用面接というシチュエーションではあるが、出会いの場、貴重な人脈作りの一環でもある
「任せる」ということ
経営とは組織の将来を考えて、持続的に利益を得て組織を発展させていくこと。
運営とは、今ある資源(人、物、金)で成果を出しつつ組織を動かしていくこと。
任せると丸投げは違う。
簡単にいえば、責任を持つのが「任せる」。
無責任なのが「丸投げ」。
丸投げのいやなところは、自分でもしっかりと出来ない事を明確な説明もしないで、相手に業務を渡しているだけで、恩恵だけ受けて問題が発生すると相手に責任を押し付ける。
過去、これで随分痛い目にあってきた。
ワンマン経営
トップの独善的な判断で強引に組織を牽引していく
リーダーシップ経営
上手な仕事の任せ方、心の持ち方、言葉の使い方を駆使して、部下の士気を高めながら組織を牽引していく
自分を最上段に置くのではなく、時には率直に部下に頼ってみる。
信頼した相手に騙されるのは、自分に魅力がなくなったから。
相手を責めるのではなく、自分の人間力を高める努力をする。
一生懸命やってもうまくいかないことは、人に任せてみる。
自分の得意なことに全く別なことに注力する。
任せた限り結果に責任を持ち、後で文句を言わない、その覚悟が部下のやる気を引き出す。
仕事の成果は部下の手柄。
失敗させたのは、トップの責任。
その度量が、組織を活気付ける。
人は、「承認」を求めている。
仕事を任せ、認め、褒めることで、士気は大いに高まる。
会社の目的は、金儲けではない、人を育てる学び舎である。
マイナス思考もすべてが悪とはかぎらない。
リスクを検証して、反省のきっかけになる。
良く笑う人には、人が集まり、仕事が集まり、お金が集まる。
笑う門には福来る。
相性の悪い人とどう付き合うか。
まず自分が心を開くと、相手も心を開いてくれるようになる。
「知識」よりも「知恵」を手に入れる努力をする。
苦しいときこそ笑顔を振りまけばうまくいく。
「大変だ」と騒ぐのではなく、「大きく変わるチャンスだ」と考える
物事すべてに「感謝」する。
「肯定語」と「否定語」の2種類の言葉がある。
笑顔と言葉はいくら使っても「無料」、いい言葉をドンドン使っていく
愚痴や相手を悪く言ってはダメ。愚痴を言って成功した人はいない。
志高く、「儲ける」のではなく「儲かる」ビジネス
お金は追っかければ逃げていく。お金のほうからやってくるようなビジネス
「円」より「縁」を大事にする
「任せる」ことの本質は、信頼関係を強くすること
「野心」ではなく「志」で一つにまとまる
「愛される」人生より「愛する」人生
「自己中心主義」より「利他中心主義」的生き方
自分で考え、自分で動けば仕事はおもしろい
「好き」が仕事になるとは限らない。きっかけさえあればどんな仕事も好きになれる
「自分のために」はすぐ飽きるが、「何かのために」は熱中できる
人件費をコストと考えず、利益同様増やしていくべき
役職は単なる「役割」にしかすぎない
「言っている事」と「やっていること」は一致しているか?
「問題提起」と「悪口・陰口」は別物。
「やる」臆病に対して「やらない」勇気も時には必要
「気遣い」は、マニュアル化・指示してもできない
自分がされていやなことは、周りに対してやらない
プロかアマか、お客様は瞬時に見抜く
会社の仕組みが悪いから、社員がミスをする
最大の失敗は、何もしないこと
経営とは組織の将来を考えて、持続的に利益を得て組織を発展させていくこと。
運営とは、今ある資源(人、物、金)で成果を出しつつ組織を動かしていくこと。
任せると丸投げは違う。
簡単にいえば、責任を持つのが「任せる」。
無責任なのが「丸投げ」。
丸投げのいやなところは、自分でもしっかりと出来ない事を明確な説明もしないで、相手に業務を渡しているだけで、恩恵だけ受けて問題が発生すると相手に責任を押し付ける。
過去、これで随分痛い目にあってきた。
ワンマン経営
トップの独善的な判断で強引に組織を牽引していく
リーダーシップ経営
上手な仕事の任せ方、心の持ち方、言葉の使い方を駆使して、部下の士気を高めながら組織を牽引していく
自分を最上段に置くのではなく、時には率直に部下に頼ってみる。
信頼した相手に騙されるのは、自分に魅力がなくなったから。
相手を責めるのではなく、自分の人間力を高める努力をする。
一生懸命やってもうまくいかないことは、人に任せてみる。
自分の得意なことに全く別なことに注力する。
任せた限り結果に責任を持ち、後で文句を言わない、その覚悟が部下のやる気を引き出す。
仕事の成果は部下の手柄。
失敗させたのは、トップの責任。
その度量が、組織を活気付ける。
人は、「承認」を求めている。
仕事を任せ、認め、褒めることで、士気は大いに高まる。
会社の目的は、金儲けではない、人を育てる学び舎である。
マイナス思考もすべてが悪とはかぎらない。
リスクを検証して、反省のきっかけになる。
良く笑う人には、人が集まり、仕事が集まり、お金が集まる。
笑う門には福来る。
相性の悪い人とどう付き合うか。
まず自分が心を開くと、相手も心を開いてくれるようになる。
「知識」よりも「知恵」を手に入れる努力をする。
苦しいときこそ笑顔を振りまけばうまくいく。
「大変だ」と騒ぐのではなく、「大きく変わるチャンスだ」と考える
物事すべてに「感謝」する。
「肯定語」と「否定語」の2種類の言葉がある。
笑顔と言葉はいくら使っても「無料」、いい言葉をドンドン使っていく
愚痴や相手を悪く言ってはダメ。愚痴を言って成功した人はいない。
志高く、「儲ける」のではなく「儲かる」ビジネス
お金は追っかければ逃げていく。お金のほうからやってくるようなビジネス
「円」より「縁」を大事にする
「任せる」ことの本質は、信頼関係を強くすること
「野心」ではなく「志」で一つにまとまる
「愛される」人生より「愛する」人生
「自己中心主義」より「利他中心主義」的生き方
自分で考え、自分で動けば仕事はおもしろい
「好き」が仕事になるとは限らない。きっかけさえあればどんな仕事も好きになれる
「自分のために」はすぐ飽きるが、「何かのために」は熱中できる
人件費をコストと考えず、利益同様増やしていくべき
役職は単なる「役割」にしかすぎない
「言っている事」と「やっていること」は一致しているか?
「問題提起」と「悪口・陰口」は別物。
「やる」臆病に対して「やらない」勇気も時には必要
「気遣い」は、マニュアル化・指示してもできない
自分がされていやなことは、周りに対してやらない
プロかアマか、お客様は瞬時に見抜く
会社の仕組みが悪いから、社員がミスをする
最大の失敗は、何もしないこと
やる気が出ない(スランプ)の時の発想法
まずイメージしてみる
私の目の前に、大きな大きな鉄の玉があります
片手で押しても、両手で押してもビクともしません
一度は諦めかけても
意を決して、コノヤロー!!と力を込めて
頑張って押し続けたところ、
ほんの少し動き始めました
そうすると
一度転がり始めると
コロコロと軽くなって
簡単に動き続けてしまいます
やる気もこの鉄の玉と同じで
最初に動き出すのはとてもたいへんですが
一度でも少し動き始めると、そのあとの行動は
スイスイと簡単にできてしまいます
やる気が起こらないのは
脳内の神経伝達物質「アセチルコリン」通称「やるき物質」が深く関係している
アセチルコリンは、少しだけ行動し始めると脳からドンドン分泌しはじめます
これを分泌させるために、まずは1分やってみるだけ
1分やれば、アセチルコリンが分泌しはじめて、やる気スイッチが入ります
何時間もやらないといけないと思うとなかなか行動に移せないが
まずはたった1分やってみるだけ
重い鉄の玉と同じで、最初はかなりきついですが
一度転がり始めれば、あとはスイスイと簡単にいくでしょう
まずイメージしてみる
私の目の前に、大きな大きな鉄の玉があります
片手で押しても、両手で押してもビクともしません
一度は諦めかけても
意を決して、コノヤロー!!と力を込めて
頑張って押し続けたところ、
ほんの少し動き始めました
そうすると
一度転がり始めると
コロコロと軽くなって
簡単に動き続けてしまいます
やる気もこの鉄の玉と同じで
最初に動き出すのはとてもたいへんですが
一度でも少し動き始めると、そのあとの行動は
スイスイと簡単にできてしまいます
やる気が起こらないのは
脳内の神経伝達物質「アセチルコリン」通称「やるき物質」が深く関係している
アセチルコリンは、少しだけ行動し始めると脳からドンドン分泌しはじめます
これを分泌させるために、まずは1分やってみるだけ
1分やれば、アセチルコリンが分泌しはじめて、やる気スイッチが入ります
何時間もやらないといけないと思うとなかなか行動に移せないが
まずはたった1分やってみるだけ
重い鉄の玉と同じで、最初はかなりきついですが
一度転がり始めれば、あとはスイスイと簡単にいくでしょう
病院以外のナースの仕事
①ツアーナース
・(旅行や研修などに添乗し、ツアー参加者の健康管理を行う)
②イベントナース
・(単発の仕事。イベント会場が勤務先となる)
③保育園
・(保育園に必要なのは保育士さんですが、0歳児や1歳児の保育を行う保育園では、看護師を募集することもあります)
④産業看護師
・(簡単にいえば“企業の保健室”が職場になります)
⑤製薬メーカー(CRC)
・(製薬メーカーに勤務する看護師、CRC(治験コーディネーター))
⑥医療機器メーカー(フィールドナース)
・(簡単に言えば、医療機器メーカーなどで働く看護師。)
⑦高齢者向け施設
・(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所、社会福祉施設、介護付き有料老人ホーム等々)
⑧訪問看護
・(在宅で療養する利用者の自宅を訪問し、医療行為や看護ケアを提供する)
⑨美容外科クリニック
・(病院でありながら、実はサービス業であるのが現状。営業ノルマが結構厳しい。「営業専門スタッフがいるから、看護師は営業なし」の職場もあり。)
⑩フリーランス・ナース
・(ナースの便利屋さん。看護師としての、技術・経験・人間力を活かして、医療・介護保険ではカバーできないニーズに対応する)
等々
※病院で働くことが嫌になってしまった理由
・委員会や係の仕事が多いのが嫌
・希望休がとりにくいのが嫌
・時短や時差出勤など、子育てに対する対策が取られにくいのが嫌
・夜勤が嫌
・忙しすぎるのが嫌
・女性メインの職場が嫌
・勉強し続けなくてはいけないのが嫌
等々
①ツアーナース
・(旅行や研修などに添乗し、ツアー参加者の健康管理を行う)
②イベントナース
・(単発の仕事。イベント会場が勤務先となる)
③保育園
・(保育園に必要なのは保育士さんですが、0歳児や1歳児の保育を行う保育園では、看護師を募集することもあります)
④産業看護師
・(簡単にいえば“企業の保健室”が職場になります)
⑤製薬メーカー(CRC)
・(製薬メーカーに勤務する看護師、CRC(治験コーディネーター))
⑥医療機器メーカー(フィールドナース)
・(簡単に言えば、医療機器メーカーなどで働く看護師。)
⑦高齢者向け施設
・(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所、社会福祉施設、介護付き有料老人ホーム等々)
⑧訪問看護
・(在宅で療養する利用者の自宅を訪問し、医療行為や看護ケアを提供する)
⑨美容外科クリニック
・(病院でありながら、実はサービス業であるのが現状。営業ノルマが結構厳しい。「営業専門スタッフがいるから、看護師は営業なし」の職場もあり。)
⑩フリーランス・ナース
・(ナースの便利屋さん。看護師としての、技術・経験・人間力を活かして、医療・介護保険ではカバーできないニーズに対応する)
等々
※病院で働くことが嫌になってしまった理由
・委員会や係の仕事が多いのが嫌
・希望休がとりにくいのが嫌
・時短や時差出勤など、子育てに対する対策が取られにくいのが嫌
・夜勤が嫌
・忙しすぎるのが嫌
・女性メインの職場が嫌
・勉強し続けなくてはいけないのが嫌
等々
会社の事務の基本(総務・労務・経理)
●会社になくてはならない総務・労務・経理
・会社の運営を支えるのが、総務・労務・経理の仕事。
・会社の経営に必要な「ヒト・モノ・カネ」を管理する。
・「ヒト・モノ・カネ」を効率的に回すことを心がける。
●縁の下の力持ち!総務の役割と心得
・総務は社員が働きやすい環境づくりが大切。
・総務には社外向けの仕事もある。会社の印象を左右する重要な仕事。
・商取引を支えるための基本的な法務知識も知っておく。
・社内:社内環境の整備・社内の制度、仕組みづくり
・社外:社外とのおつきあい・広報宣伝活動・会社の法務
●社員の安心を守る!労務の役割と心得
・労務は社員の採用から退職まであらゆる業務を担当。
・労務は社員の働き方のルールについても管理する。
・労務は社員の社会保険の手続きなども一部代行する。
・人事:就業規則の整備・採用、入社、退職の手続き
・給与:給与計算・社会保険、労働保険事務
●会社経営のキモ!経理の役割と心得
・経理は会社のあらゆるお金の動きを管理・記録する。
・日々の帳簿づけをまとめたものが決算。
・経理は年に一度の決算と会社の税務も行う。
・帳簿:社内のお金の記録、管理・請求、支払い
・経営:決算・税務
★「労働保険・社会保険」と「税金」の基本
●労働保険・社会保険
・労働保険:労災保険・雇用保険
・社会保険:健康保険・厚生年金保険・介護保険
●給与から差し引く税金
・所得税
・住民税
●会社が納付するおもな税金
すべての会社が申告・納付するおもな税金
・法人税(税務署)
・地方法人税(税務署)
・法人住民税(県・市)
・法人事業税(県)
・地方法人特別税(県)
売上高などに応じて支払うおもな税金
・消費税(税務署)
・印紙税
●会社になくてはならない総務・労務・経理
・会社の運営を支えるのが、総務・労務・経理の仕事。
・会社の経営に必要な「ヒト・モノ・カネ」を管理する。
・「ヒト・モノ・カネ」を効率的に回すことを心がける。
●縁の下の力持ち!総務の役割と心得
・総務は社員が働きやすい環境づくりが大切。
・総務には社外向けの仕事もある。会社の印象を左右する重要な仕事。
・商取引を支えるための基本的な法務知識も知っておく。
・社内:社内環境の整備・社内の制度、仕組みづくり
・社外:社外とのおつきあい・広報宣伝活動・会社の法務
●社員の安心を守る!労務の役割と心得
・労務は社員の採用から退職まであらゆる業務を担当。
・労務は社員の働き方のルールについても管理する。
・労務は社員の社会保険の手続きなども一部代行する。
・人事:就業規則の整備・採用、入社、退職の手続き
・給与:給与計算・社会保険、労働保険事務
●会社経営のキモ!経理の役割と心得
・経理は会社のあらゆるお金の動きを管理・記録する。
・日々の帳簿づけをまとめたものが決算。
・経理は年に一度の決算と会社の税務も行う。
・帳簿:社内のお金の記録、管理・請求、支払い
・経営:決算・税務
★「労働保険・社会保険」と「税金」の基本
●労働保険・社会保険
・労働保険:労災保険・雇用保険
・社会保険:健康保険・厚生年金保険・介護保険
●給与から差し引く税金
・所得税
・住民税
●会社が納付するおもな税金
すべての会社が申告・納付するおもな税金
・法人税(税務署)
・地方法人税(税務署)
・法人住民税(県・市)
・法人事業税(県)
・地方法人特別税(県)
売上高などに応じて支払うおもな税金
・消費税(税務署)
・印紙税
小さい会社で働くメリット
①小さい会社は自分の影響力が大きい
100人の中の1人として働くのと、10人の中の1人として働くのでは、当然一社員が会社に与える影響は違ってきます。
社員が少ない組織ほど、1人の社員の行動や業績が、会社のブランドや売り上げに直に響いてきます。
責任が重くなると言えますが、評価されやすいとも言えます。
②小さい会社は自分好みの環境を作りやすい
自分の影響力が大きいことは、自分の望む職場環境を作りやすくなることを意味します。
社員が100人もいれば、一社員の都合に合わせて組織や制度を変えることはできませんが、5人だけの会社であれば、一社員の希望をすぐにトップに伝えることができます。
合理的な理由さえあれば、すぐに環境を変えることができます。
小さい会社では、一社員のモチベーションや能率が業績に直に響くので、各社員が心地よく働ける環境をできるだけ用意しなければならない、という事情もあります。
③小さい会社は社内業務が少ない
これは業態や職能、会社の体質などにもよりますが、大きな会社ほど社内業務が多くなる傾向があります。
経験も価値観も異なる多様な社員が数多く所属する組織を束ねるには、統一した仕組みやルールが必要になり、それらを維持するための仕事が必要になるからです。
社内業務が好きでたまらない人には願ってもない環境かもしれませんが、多くの人は社内業務の多さに不満を感じ、顧客に向き合う本来の仕事がしたいと思います。
小さい会社では、このような組織を維持するための仕事が少なくてすむため、本来の業務に集中しやすくなります。
④小さい会社は社会に働きかけやすい
社内業務が少ないから、外の世界に向けての仕事をする時間が多くなります。
また組織の階層構造が浅く、意思決定プロセスがシンプルなため、自分で決断する機会が多くなり、仕事を通じて自分の考えを社会に発信しやすくなります。
大きい会社では社内業務が多くなり、また複数の意思決定権者の承認の元に活動することも多いため、自分の意志で社会に働きかけている感覚が薄くなりがちです。
小さい会社は社内で完結できることが少ないため、必然的に外に向かわなくてはならなくなる、とも言えます。
⑤小さい会社は外との交流に積極的
小さい会社は、少ない社内リソースだけでは仕事が完結しないことが多いため、外部の人との繋がりが増えていきます。
また会社が小さいことを自覚し、外に向かって積極的に出ていかないと取り残されるかも、と危機感を持っている人が多いため、外部と積極的に繋がる風土があったりします。
大きな会社では社内で仕事が完結してしまうことが多く、また社外の人と接するときも、人対人というより、会社対会社の割り切った付き合いという面が強くなりがちで、社外での濃い人脈が広がりにくい傾向があります。
⑥小さい会社は人間関係が良好
小さい会社においては一社員の影響力が強い故に、人間関係で大きな問題が発生すると、致命的な結果を招きます。
小さい会社で働く人たちはそのことをよく分かっているため、特に採用では、経験やスキル以上に、社内でうまくやっていけるか、という点を重視します。
結果、小さい会社は良好な人間関係を維持しているケースが多いです。
大きな会社では現場が採用に深くタッチできないことも多く、人事異動などのアンコントローラブルな要因も重なるため、運が悪いと最悪の人間関係の中で仕事をする羽目になります。
⑦小さい会社は自分が必要とされている感が強い
良くも悪くもですが、小さい会社は人が少ないので、仕事が属人的になりがちです。
会社にとって、属人的であることは組織としてのあやうさに繋がるため、「あなたがいなくても会社は回る」という状況を作らなければなりません。
しかし、リソースの少ない小さな会社はそうはなれないので、結果的に「あなたがいなくては会社が成り立たない」となりがちです。
会社をサービス提供システムと考えると属人的すぎるのは問題なのですが、働く当人としては、会社に必要とされていることを実感し、周囲の人の感謝や評価を直に感じながら働くことができます。
⑧小さい会社は経営を間近で見ることができる
小さい会社では目の届くところに社長や副社長がいて、これまた良くも悪くもその行動を間近に見ることができます。
経営に関する行動には、マーケティング、ブランディング、人事、法務、財務など、ビジネスの本質となるエッセンスが数多く含まれています。
これを近くで体験することは、あらゆる職種や職能にとってプラスになるでしょう。
一方、大きな会社は現場からは経営的な動きが見えにくく、経営に関与できる立場ではない限り、経営を直に感じることは稀です。
それ故に、仕事を近視眼的に見てしまい、近視眼的にキャリアプランを立ててしまう危険性があります。
⑨小さい会社は幅広く仕事を経験できる
小さい会社は分業されていないことが多いです。
専門性を追求したいと思う人には好ましくない環境のように思えるでしょうが、隣り合う領域の経験を積むことはスキルに深みを与え、結果的にプラスになることが多いです。
一方、大きな会社では分業化が進んでいることが多いです。
専門性が追求できる反面、さらなるスキルアップを目指して新たなフィールドに足を踏み入れたいとき、あるいは市場環境が変わってその専門スキルが陳腐化したとき、経験の幅の狭さが障壁となり、次のステップへ進めない、ということが起こりえます。
⑩小さい会社で働くとたくましく生きられる
小さい会社で働いていれば、経営を間近で見ながら、幅広く仕事を経験するので、最悪会社がなくなっても他でやっていけるような能力が身に付きやすいです。
大きな会社にいると、その会社の完成された文化(=閉ざされた文化)に依存して仕事をし続けるので、会社が倒産したり、リストラの対象となったりした際に潰しが効かず、収入や社会的地位を大きく下げるリスクが高まります。
大企業で働くというのは、変化の激しい今の時代を生き抜くのに十分な変化への適応力を磨くには、ある意味不利な環境であるとも言えます。
⑪小さい会社は良い肩書が手に入りやすい
肩書なんて、と思われるかもしれませんが、肩書によって周囲の目が変わり、自分が携わる仕事の質も変わります。
大企業で課長になれる努力で、中小企業だったら副社長になれるかもしれません。
課長は、世の中一般の課長イメージで見られ、課長的な仕事が舞い込んできます。
中小企業の副社長には、それが例え中小企業であっても、企業のNo.2であると見られ、副社長に相応しい仕事が舞い込みます。
そして立場が変われば、スキルやモノを見る目も変わってきます。
たとえば、異業種交流会に有名な大企業の課長と見知らぬ中小企業の副社長がいて、どちらか一方としかお話しできないとしたら、ふつうは、後者の方を選びます。
なぜなら自分で意思決定できる立場にいる人の方が経験も豊富で、物事を動かす力や責任も大きい傾向があるため、同じ時間を費やすのであれば、そういう人と話がしたいと思います。
そうやって副社長に近い立場の人が集まってきます。
このことは、キャリアパスに案外大きな影響を与えます。
⑫小さい会社は自分の力を試せる
小さい会社で働くと言い訳が効きません。
例えば「会社が自分の好きな仕事をさせてくれない」などと言おうものなら、自分の好きな仕事ができるように会社を変えられないあなたに問題があるんじゃないの?と言われてしまいます。
小さい会社は自分の力で変えられる領域が広いので、ごまかしがきかないとも言えますが、自分の本来の能力をストレートに発揮できるとも言えます。
⑬小さい会社は収入を上げやすい
小さい会社は一社員の貢献度の証明が比較的簡単で、給与の算定方法もシステマティックではないので、会社の業績さえ上げられれば、割とすぐに給与に反映されます。
あるいは目標の収入があった時に、その収入を得るためにどうすればいいかをトップに相談し、それに近づく手段をきちんと教えてもらうこともできます。
大きな会社でも最近は柔軟な会社も増えてきていますが、一社員の業績への貢献度が図りにくく、また給与システムがある程度確立しているため、ドンと給与を上げるようなイレギュラー処理は難しく、どうしても平均的なところに収まりがちです。
⑭小さい会社は実はリスクが少ない
今まで挙げた小さい会社のメリットが全てを物語りますが、大きな会社だからリスクが少ないとは言い切れません。
大きな会社は一見安定していますが、会社もそこで働く人も、大きな社会的変化に対応しにくくなりがちです。小さな会社は心もとなく見えますが、そこで働いていると、自分の力次第で社会的変化に対応できるようになります。
例えばJALや東京電力で働いている人は、入社時に今の様な状況を予想できたでしょうか。
その状況を一社員の努力で回避できたでしょうか。
そこでリストラになった時に、外の世界でもたくましく生きていけるでしょうか。
これはタイタニック号と手漕ぎボートの関係によく例えられますが、巨大氷山が次から次へと流れてくるこの時代に、タイタニック号と手漕ぎボートのどちらに乗り込む方がリスクは少ないでしょうか。
正解はありませんが、大きな会社に勤める時には、そのリスクを十分に考えて、自分の立ち振る舞い方を決めておく必要はあるでしょう。
●まとめ
小さい会社で働くのも決して悪い選択ではないでしょう。
もちろん、人と同じように会社にも個性はあります。
上記のような小さい企業のメリットのいくつかをあわせ持つ大企業もあれば、小さい会社でもボスが激しいワンマンで大企業並みに窮屈な会社もあります。
しかし、傾向としては、小さい会社には上記のようなメリットがあると言えるのではないでしょうか。
ただし、これらのメリットを、本当にメリットとして享受するには一つ前提条件があります。
それは「主体的に行動したい人である」という条件です。
できあがっている組織やブランドに乗っかりたい、優秀な人にあやかりたい、誰かに引っ張ってもらいたい、自分は何もせずできるだけ楽して生きていきたい、という考えの方には、上記のメリットの多くは、むしろデメリットとして降りかかってくることでしょう。
結局、小さな会社で働くことが良い経験になるか、悪い経験になるかは、その人次第です。
自分がイニシアチブを握って自分の仕事やキャリアを築いていきたいと強く思っている人は、会社が大きかろうが、小さかろうが、どちらの経験もうまく活用して力強く生きていけます。
働く会社を選ぶときには、会社の規模にはあまりこだわらず、自分のしたいこと、楽しめること、将来のビジョン、そしてその会社と自分との相性を優先して、会社を選んでいっていいのではないでしょうか。
①小さい会社は自分の影響力が大きい
100人の中の1人として働くのと、10人の中の1人として働くのでは、当然一社員が会社に与える影響は違ってきます。
社員が少ない組織ほど、1人の社員の行動や業績が、会社のブランドや売り上げに直に響いてきます。
責任が重くなると言えますが、評価されやすいとも言えます。
②小さい会社は自分好みの環境を作りやすい
自分の影響力が大きいことは、自分の望む職場環境を作りやすくなることを意味します。
社員が100人もいれば、一社員の都合に合わせて組織や制度を変えることはできませんが、5人だけの会社であれば、一社員の希望をすぐにトップに伝えることができます。
合理的な理由さえあれば、すぐに環境を変えることができます。
小さい会社では、一社員のモチベーションや能率が業績に直に響くので、各社員が心地よく働ける環境をできるだけ用意しなければならない、という事情もあります。
③小さい会社は社内業務が少ない
これは業態や職能、会社の体質などにもよりますが、大きな会社ほど社内業務が多くなる傾向があります。
経験も価値観も異なる多様な社員が数多く所属する組織を束ねるには、統一した仕組みやルールが必要になり、それらを維持するための仕事が必要になるからです。
社内業務が好きでたまらない人には願ってもない環境かもしれませんが、多くの人は社内業務の多さに不満を感じ、顧客に向き合う本来の仕事がしたいと思います。
小さい会社では、このような組織を維持するための仕事が少なくてすむため、本来の業務に集中しやすくなります。
④小さい会社は社会に働きかけやすい
社内業務が少ないから、外の世界に向けての仕事をする時間が多くなります。
また組織の階層構造が浅く、意思決定プロセスがシンプルなため、自分で決断する機会が多くなり、仕事を通じて自分の考えを社会に発信しやすくなります。
大きい会社では社内業務が多くなり、また複数の意思決定権者の承認の元に活動することも多いため、自分の意志で社会に働きかけている感覚が薄くなりがちです。
小さい会社は社内で完結できることが少ないため、必然的に外に向かわなくてはならなくなる、とも言えます。
⑤小さい会社は外との交流に積極的
小さい会社は、少ない社内リソースだけでは仕事が完結しないことが多いため、外部の人との繋がりが増えていきます。
また会社が小さいことを自覚し、外に向かって積極的に出ていかないと取り残されるかも、と危機感を持っている人が多いため、外部と積極的に繋がる風土があったりします。
大きな会社では社内で仕事が完結してしまうことが多く、また社外の人と接するときも、人対人というより、会社対会社の割り切った付き合いという面が強くなりがちで、社外での濃い人脈が広がりにくい傾向があります。
⑥小さい会社は人間関係が良好
小さい会社においては一社員の影響力が強い故に、人間関係で大きな問題が発生すると、致命的な結果を招きます。
小さい会社で働く人たちはそのことをよく分かっているため、特に採用では、経験やスキル以上に、社内でうまくやっていけるか、という点を重視します。
結果、小さい会社は良好な人間関係を維持しているケースが多いです。
大きな会社では現場が採用に深くタッチできないことも多く、人事異動などのアンコントローラブルな要因も重なるため、運が悪いと最悪の人間関係の中で仕事をする羽目になります。
⑦小さい会社は自分が必要とされている感が強い
良くも悪くもですが、小さい会社は人が少ないので、仕事が属人的になりがちです。
会社にとって、属人的であることは組織としてのあやうさに繋がるため、「あなたがいなくても会社は回る」という状況を作らなければなりません。
しかし、リソースの少ない小さな会社はそうはなれないので、結果的に「あなたがいなくては会社が成り立たない」となりがちです。
会社をサービス提供システムと考えると属人的すぎるのは問題なのですが、働く当人としては、会社に必要とされていることを実感し、周囲の人の感謝や評価を直に感じながら働くことができます。
⑧小さい会社は経営を間近で見ることができる
小さい会社では目の届くところに社長や副社長がいて、これまた良くも悪くもその行動を間近に見ることができます。
経営に関する行動には、マーケティング、ブランディング、人事、法務、財務など、ビジネスの本質となるエッセンスが数多く含まれています。
これを近くで体験することは、あらゆる職種や職能にとってプラスになるでしょう。
一方、大きな会社は現場からは経営的な動きが見えにくく、経営に関与できる立場ではない限り、経営を直に感じることは稀です。
それ故に、仕事を近視眼的に見てしまい、近視眼的にキャリアプランを立ててしまう危険性があります。
⑨小さい会社は幅広く仕事を経験できる
小さい会社は分業されていないことが多いです。
専門性を追求したいと思う人には好ましくない環境のように思えるでしょうが、隣り合う領域の経験を積むことはスキルに深みを与え、結果的にプラスになることが多いです。
一方、大きな会社では分業化が進んでいることが多いです。
専門性が追求できる反面、さらなるスキルアップを目指して新たなフィールドに足を踏み入れたいとき、あるいは市場環境が変わってその専門スキルが陳腐化したとき、経験の幅の狭さが障壁となり、次のステップへ進めない、ということが起こりえます。
⑩小さい会社で働くとたくましく生きられる
小さい会社で働いていれば、経営を間近で見ながら、幅広く仕事を経験するので、最悪会社がなくなっても他でやっていけるような能力が身に付きやすいです。
大きな会社にいると、その会社の完成された文化(=閉ざされた文化)に依存して仕事をし続けるので、会社が倒産したり、リストラの対象となったりした際に潰しが効かず、収入や社会的地位を大きく下げるリスクが高まります。
大企業で働くというのは、変化の激しい今の時代を生き抜くのに十分な変化への適応力を磨くには、ある意味不利な環境であるとも言えます。
⑪小さい会社は良い肩書が手に入りやすい
肩書なんて、と思われるかもしれませんが、肩書によって周囲の目が変わり、自分が携わる仕事の質も変わります。
大企業で課長になれる努力で、中小企業だったら副社長になれるかもしれません。
課長は、世の中一般の課長イメージで見られ、課長的な仕事が舞い込んできます。
中小企業の副社長には、それが例え中小企業であっても、企業のNo.2であると見られ、副社長に相応しい仕事が舞い込みます。
そして立場が変われば、スキルやモノを見る目も変わってきます。
たとえば、異業種交流会に有名な大企業の課長と見知らぬ中小企業の副社長がいて、どちらか一方としかお話しできないとしたら、ふつうは、後者の方を選びます。
なぜなら自分で意思決定できる立場にいる人の方が経験も豊富で、物事を動かす力や責任も大きい傾向があるため、同じ時間を費やすのであれば、そういう人と話がしたいと思います。
そうやって副社長に近い立場の人が集まってきます。
このことは、キャリアパスに案外大きな影響を与えます。
⑫小さい会社は自分の力を試せる
小さい会社で働くと言い訳が効きません。
例えば「会社が自分の好きな仕事をさせてくれない」などと言おうものなら、自分の好きな仕事ができるように会社を変えられないあなたに問題があるんじゃないの?と言われてしまいます。
小さい会社は自分の力で変えられる領域が広いので、ごまかしがきかないとも言えますが、自分の本来の能力をストレートに発揮できるとも言えます。
⑬小さい会社は収入を上げやすい
小さい会社は一社員の貢献度の証明が比較的簡単で、給与の算定方法もシステマティックではないので、会社の業績さえ上げられれば、割とすぐに給与に反映されます。
あるいは目標の収入があった時に、その収入を得るためにどうすればいいかをトップに相談し、それに近づく手段をきちんと教えてもらうこともできます。
大きな会社でも最近は柔軟な会社も増えてきていますが、一社員の業績への貢献度が図りにくく、また給与システムがある程度確立しているため、ドンと給与を上げるようなイレギュラー処理は難しく、どうしても平均的なところに収まりがちです。
⑭小さい会社は実はリスクが少ない
今まで挙げた小さい会社のメリットが全てを物語りますが、大きな会社だからリスクが少ないとは言い切れません。
大きな会社は一見安定していますが、会社もそこで働く人も、大きな社会的変化に対応しにくくなりがちです。小さな会社は心もとなく見えますが、そこで働いていると、自分の力次第で社会的変化に対応できるようになります。
例えばJALや東京電力で働いている人は、入社時に今の様な状況を予想できたでしょうか。
その状況を一社員の努力で回避できたでしょうか。
そこでリストラになった時に、外の世界でもたくましく生きていけるでしょうか。
これはタイタニック号と手漕ぎボートの関係によく例えられますが、巨大氷山が次から次へと流れてくるこの時代に、タイタニック号と手漕ぎボートのどちらに乗り込む方がリスクは少ないでしょうか。
正解はありませんが、大きな会社に勤める時には、そのリスクを十分に考えて、自分の立ち振る舞い方を決めておく必要はあるでしょう。
●まとめ
小さい会社で働くのも決して悪い選択ではないでしょう。
もちろん、人と同じように会社にも個性はあります。
上記のような小さい企業のメリットのいくつかをあわせ持つ大企業もあれば、小さい会社でもボスが激しいワンマンで大企業並みに窮屈な会社もあります。
しかし、傾向としては、小さい会社には上記のようなメリットがあると言えるのではないでしょうか。
ただし、これらのメリットを、本当にメリットとして享受するには一つ前提条件があります。
それは「主体的に行動したい人である」という条件です。
できあがっている組織やブランドに乗っかりたい、優秀な人にあやかりたい、誰かに引っ張ってもらいたい、自分は何もせずできるだけ楽して生きていきたい、という考えの方には、上記のメリットの多くは、むしろデメリットとして降りかかってくることでしょう。
結局、小さな会社で働くことが良い経験になるか、悪い経験になるかは、その人次第です。
自分がイニシアチブを握って自分の仕事やキャリアを築いていきたいと強く思っている人は、会社が大きかろうが、小さかろうが、どちらの経験もうまく活用して力強く生きていけます。
働く会社を選ぶときには、会社の規模にはあまりこだわらず、自分のしたいこと、楽しめること、将来のビジョン、そしてその会社と自分との相性を優先して、会社を選んでいっていいのではないでしょうか。
事業展開・行動計画
事業理念、「三つの宝」に則り進めていく
●子は世の宝
「小児特化型訪問看護ステーション」の開設
・訪問看護師3名(管理者含む・認可に必要な最低人数)の採用
・事業所の確保(地理的条件から沖縄市中央付近へ移転・第一候補としてコリンザ・テナント入居(一月中旬入居募集))
・開設費用の確保、認可申請準備
●安心・健康は地域の宝
看護師を有効な社会資源として地域貢献事業に取り組み、医療施設・機関以外での看護師の活躍の場を、創造・開拓していく。
・担当メンバーの採用(看護サービス企画・プランナー他)
・「企業訪問健康チェック・相談サービス」他、具体的提供サービスの開発
・事業全体の収益の柱として、収益性の確保
●看護師は、医療・福祉業界の宝
「人」がすべての事業、安定雇用と就業満足度の確保
・お互いのマッチングミスのない採用
・給与の安定支給とベースアップの確保
・お互いが安心できる、就業規則・福利厚生の確保
事業理念、「三つの宝」に則り進めていく
●子は世の宝
「小児特化型訪問看護ステーション」の開設
・訪問看護師3名(管理者含む・認可に必要な最低人数)の採用
・事業所の確保(地理的条件から沖縄市中央付近へ移転・第一候補としてコリンザ・テナント入居(一月中旬入居募集))
・開設費用の確保、認可申請準備
●安心・健康は地域の宝
看護師を有効な社会資源として地域貢献事業に取り組み、医療施設・機関以外での看護師の活躍の場を、創造・開拓していく。
・担当メンバーの採用(看護サービス企画・プランナー他)
・「企業訪問健康チェック・相談サービス」他、具体的提供サービスの開発
・事業全体の収益の柱として、収益性の確保
●看護師は、医療・福祉業界の宝
「人」がすべての事業、安定雇用と就業満足度の確保
・お互いのマッチングミスのない採用
・給与の安定支給とベースアップの確保
・お互いが安心できる、就業規則・福利厚生の確保
ソーシャルワーク・ナース(看護師) 募集
●職種
ソーシャルワーク・ナース(看護師)
●仕事の内容
・健康相談、生活支援、外出支援、ツアーナース、イベントナース、講演など
・OJT、Off-JT研修あり
・看護師を有効な社会資源として地域貢献事業に取り組み、医療施設・機関以外の地域社会で、医療・介護保険制度に頼らない看護師の活躍の場を、創造・開拓していきます。
※求める人物像
・新しいことにチャレンジすることに喜びとやりがいを見い出せる方
・業務・運営に関しても主体性をもって積極的に提案・アドバイスのできる方
・一定のコミュニケーションスキルをお持ちの方
※新規事業のスターティングメンバーとして、ともに盛り上げていく「同志」を募集しています。
●雇用形態
正社員(雇用期間の定めなし)
学歴不問、必要な経験等不問、年齢不問
必要な免許・資格:普通自動車免許、看護師(正・准)免許
●賃金
基本給:200,000円、手当:車両手当・3,000円、通信手当・2,000円、合計:205,000円
※採用後に労災保険、雇用保険、社会保険に加入
※業績に応じて昇給・賞与あり
※通勤手当:実費(上限なし)
●就業時間・休日等
8:30~17:30(休憩1h)
完全週休二日(土、日、祝祭日、年末年始)
●備考
※沖縄市中央へ移転予定あり(通勤が可能な方)
※ハローワークを通して求人募集いたします。詳細はハローワークまで。
●創業間もない法人であり
「子は世の宝」
「安心・健康は地域の宝」
「看護師は医療・福祉業界の宝」
この三つの宝を基本コンセプトにして
事業展開を図って行きます。
●職種
ソーシャルワーク・ナース(看護師)
●仕事の内容
・健康相談、生活支援、外出支援、ツアーナース、イベントナース、講演など
・OJT、Off-JT研修あり
・看護師を有効な社会資源として地域貢献事業に取り組み、医療施設・機関以外の地域社会で、医療・介護保険制度に頼らない看護師の活躍の場を、創造・開拓していきます。
※求める人物像
・新しいことにチャレンジすることに喜びとやりがいを見い出せる方
・業務・運営に関しても主体性をもって積極的に提案・アドバイスのできる方
・一定のコミュニケーションスキルをお持ちの方
※新規事業のスターティングメンバーとして、ともに盛り上げていく「同志」を募集しています。
●雇用形態
正社員(雇用期間の定めなし)
学歴不問、必要な経験等不問、年齢不問
必要な免許・資格:普通自動車免許、看護師(正・准)免許
●賃金
基本給:200,000円、手当:車両手当・3,000円、通信手当・2,000円、合計:205,000円
※採用後に労災保険、雇用保険、社会保険に加入
※業績に応じて昇給・賞与あり
※通勤手当:実費(上限なし)
●就業時間・休日等
8:30~17:30(休憩1h)
完全週休二日(土、日、祝祭日、年末年始)
●備考
※沖縄市中央へ移転予定あり(通勤が可能な方)
※ハローワークを通して求人募集いたします。詳細はハローワークまで。
●創業間もない法人であり
「子は世の宝」
「安心・健康は地域の宝」
「看護師は医療・福祉業界の宝」
この三つの宝を基本コンセプトにして
事業展開を図って行きます。
「楽な仕事」と「楽しい仕事」
脳科学的に見ると、脳は大量にエネルギーを消費するので無意識に楽する(脳のエネルギー消費量を押さえる)ように働きますが、そうすると筋肉と同じで負荷がかからないので脳は発達・成長しません。
①「楽な仕事」だが、「楽しい仕事」では無い
②「楽な仕事」では無いが、「楽しい仕事」である
③「楽な仕事」であり、「楽しい仕事」でもある
一見③を選びたくなるが、惰性に流された「楽する」状況が常態化(手を抜く、逃げる、考えない)すると、挑戦をした先にある、達成感・充実感を味わえる、本当の「楽しい仕事」を経験できない。
迷わず②を選び、苦労・苦痛・疲労感を味わい「楽する」ことは出来ないが、充実・夢中・達成感を味わえる「楽しい」仕事と人生を送りたい。
脳科学的に見ると、脳は大量にエネルギーを消費するので無意識に楽する(脳のエネルギー消費量を押さえる)ように働きますが、そうすると筋肉と同じで負荷がかからないので脳は発達・成長しません。
①「楽な仕事」だが、「楽しい仕事」では無い
②「楽な仕事」では無いが、「楽しい仕事」である
③「楽な仕事」であり、「楽しい仕事」でもある
一見③を選びたくなるが、惰性に流された「楽する」状況が常態化(手を抜く、逃げる、考えない)すると、挑戦をした先にある、達成感・充実感を味わえる、本当の「楽しい仕事」を経験できない。
迷わず②を選び、苦労・苦痛・疲労感を味わい「楽する」ことは出来ないが、充実・夢中・達成感を味わえる「楽しい」仕事と人生を送りたい。
●事業内容
「小児特化型訪問看護ステーション」の開設や、看護師を有効な社会資源と位置づけ、社会貢献事業の一環として、医療・介護保険制度に頼らない、新たな看護サービスビジネスを創造・展開していきます。
●法人の特徴
創業まもない法人であり、「子は世の宝」・「安心・健康は地域の宝」・「看護師は医療・福祉業界の宝」、この三つの宝を基本コンセプトにして、新規事業展開を図っていきます。
「小児特化型訪問看護ステーション」の開設や、看護師を有効な社会資源と位置づけ、社会貢献事業の一環として、医療・介護保険制度に頼らない、新たな看護サービスビジネスを創造・展開していきます。
●法人の特徴
創業まもない法人であり、「子は世の宝」・「安心・健康は地域の宝」・「看護師は医療・福祉業界の宝」、この三つの宝を基本コンセプトにして、新規事業展開を図っていきます。
本日良い出会いがありました
北海道在住の専門家との電話とメールのやりとりですが
鋭い指摘とアドバイス
初動体制と認識の甘さを痛感させられました
目が覚める思い
感謝!
全力で前進あるのみ
餅は餅屋、生兵法はけがの元、我以外皆師なり
ギブアンドテイク、お互いが高めあい利する、関係づくりが人脈づくりの基本ではないか、肝に銘じていかねば・・・
北海道在住の専門家との電話とメールのやりとりですが
鋭い指摘とアドバイス
初動体制と認識の甘さを痛感させられました
目が覚める思い
感謝!
全力で前進あるのみ
餅は餅屋、生兵法はけがの元、我以外皆師なり
ギブアンドテイク、お互いが高めあい利する、関係づくりが人脈づくりの基本ではないか、肝に銘じていかねば・・・
従業員のやる気や不満の要因
●動機づけ要因
(これが満たされると、従業員はやる気を出します)
①仕事のやりがい
・作業目的の周知
・顧客志向の浸透
・経営参画意識の浸透
・業務方針の明確化
②仕事の達成感
・挑戦する風土
・適正な目標の設定
・達成度の見える化
・表彰などの心理的報酬
③責任の増大
・役職や肩書の付与
・部下や後輩の増加
・利益目標の設定
・使命や期待の伝達
④自己の成長
・身につけるべき知識や能力の明確化
・キャリアパスの明確化
●衛生要因
(これが満たされないと、従業員は不満を募らせます。
①会社の方針
・経営理念の浸透
・経営方針の明確化
・信賞必罰の徹底
・経営者への信頼向上
②賃金
(本人なりの基準がある)
・生活できるかどうか
・同僚や他社と比べてどうか
・自分の頑張りや貢献度と比べてどうか
③作業環境
・作業条件や作業環境の悪さ
・業務負荷の不公正さ
④人間関係
・コミュニケーションの活性化
・報告・連絡・相談の強化
・問題がある従業員の再教育または排除
⑤雇用の安定性
・理由が不透明な解雇
・極端な成果主義
●動機づけ要因
(これが満たされると、従業員はやる気を出します)
①仕事のやりがい
・作業目的の周知
・顧客志向の浸透
・経営参画意識の浸透
・業務方針の明確化
②仕事の達成感
・挑戦する風土
・適正な目標の設定
・達成度の見える化
・表彰などの心理的報酬
③責任の増大
・役職や肩書の付与
・部下や後輩の増加
・利益目標の設定
・使命や期待の伝達
④自己の成長
・身につけるべき知識や能力の明確化
・キャリアパスの明確化
●衛生要因
(これが満たされないと、従業員は不満を募らせます。
①会社の方針
・経営理念の浸透
・経営方針の明確化
・信賞必罰の徹底
・経営者への信頼向上
②賃金
(本人なりの基準がある)
・生活できるかどうか
・同僚や他社と比べてどうか
・自分の頑張りや貢献度と比べてどうか
③作業環境
・作業条件や作業環境の悪さ
・業務負荷の不公正さ
④人間関係
・コミュニケーションの活性化
・報告・連絡・相談の強化
・問題がある従業員の再教育または排除
⑤雇用の安定性
・理由が不透明な解雇
・極端な成果主義
●ビートたけし
自分のために死んでくれる人間が何人いるよりも、そいつのためなら命をかけられるって友達が1人でもいる方が、人間としては幸せだと思う
他人への気遣いで大切なのは、話を聞いてやることだ。人間は歳を取ると、どういうわけかこれが苦手になるらしい
夢は、夢。目標とは違うんだけど、勘違いしてる奴が 「夢をもっていきなきゃ」なんてごちゃごちゃにしている
●美輪明宏
不幸な家庭に育った人は強く生きる能力を持つ人。あながち不幸ではない
世の中には人には言えない苦しみや地獄を抱えた人もいる。それでもニコニコ朗らかに生きる強い人がいる
悩んで落ち込んだとき、必要なのは理性。いらないのは感情。原因をクールに分析して、解決方法を見つける習慣を
●ピーター・ドラッカー
複雑なものはうまくいかない
仕事ができる組織は仕事を楽しんでいる
間違いや失敗を犯したことのない者というのは、単に無難なこと、安全なこと、つまらないことしか、やってこなかっただけである。逆に優れている者ほど、数えきれない間違いを犯すものであり、これは常に新しいことに挑戦している証拠である
自分のために死んでくれる人間が何人いるよりも、そいつのためなら命をかけられるって友達が1人でもいる方が、人間としては幸せだと思う
他人への気遣いで大切なのは、話を聞いてやることだ。人間は歳を取ると、どういうわけかこれが苦手になるらしい
夢は、夢。目標とは違うんだけど、勘違いしてる奴が 「夢をもっていきなきゃ」なんてごちゃごちゃにしている
●美輪明宏
不幸な家庭に育った人は強く生きる能力を持つ人。あながち不幸ではない
世の中には人には言えない苦しみや地獄を抱えた人もいる。それでもニコニコ朗らかに生きる強い人がいる
悩んで落ち込んだとき、必要なのは理性。いらないのは感情。原因をクールに分析して、解決方法を見つける習慣を
●ピーター・ドラッカー
複雑なものはうまくいかない
仕事ができる組織は仕事を楽しんでいる
間違いや失敗を犯したことのない者というのは、単に無難なこと、安全なこと、つまらないことしか、やってこなかっただけである。逆に優れている者ほど、数えきれない間違いを犯すものであり、これは常に新しいことに挑戦している証拠である
人は何故?何のために生きる?
「奉仕」
1人称だけで生きていると、飽きるし行き詰ってしまう。
あの頃、バブルを謳歌し、物欲・自己顕示欲にまみれ自己実現に向け励んでいたが、しばらくして、飽き、疑問がわいてきた
自分以外の何かのために行動するときは、集中し夢中になり自分の存在感・高揚感を味わえる。
愛する人の為、家族の為、仲間の為、社会の為・・・・
よく聞く話で、海外セレブが富と名声を得て自己実現を果たした次に他己実現に向かい、社会奉仕やボランティア活動に励む
雑念に惑わされず、夢中になり達成感を味わえる充実した人生を歩みたい
「奉仕」
1人称だけで生きていると、飽きるし行き詰ってしまう。
あの頃、バブルを謳歌し、物欲・自己顕示欲にまみれ自己実現に向け励んでいたが、しばらくして、飽き、疑問がわいてきた
自分以外の何かのために行動するときは、集中し夢中になり自分の存在感・高揚感を味わえる。
愛する人の為、家族の為、仲間の為、社会の為・・・・
よく聞く話で、海外セレブが富と名声を得て自己実現を果たした次に他己実現に向かい、社会奉仕やボランティア活動に励む
雑念に惑わされず、夢中になり達成感を味わえる充実した人生を歩みたい
当法人では、小児特化型訪問看護ステーション事業と平行して、地域貢献事業としてのビジネス展開を図っていきます。
●商材としての看護師の活用法
①既存ビジネスに看護師(医療的技術・知識・経験)という付加価値をつける
(例)
・看護師の運行する介護タクシー
・看護師資格保持のツアーコンダクター
・看護師によるアロマテラピー
・看護師によるベビーシッター
・看護師によるレクリエーション・コーディネーター
等々
②新たな看護ビジネスを創造する
(ニーズを生む社会状況)
・少子高齢化社会
・生活習慣病をはじめとする慢性疾患の増加
・医療費の増大
・ストレス社会
・家族関係の変化
・病気治療から疾病予防・健康増進へ
・救命・延命中心の医療からQOL(クオリティ・オブ・ライフ、人生の内容・質)向上へ
医療のあり方が、病院中心、治療中心から、地域の中で寄り添う医療へシフトしていく社会情勢を踏まえて、公的サービスのニッチを埋める民間ビジネスとして、看護師を活用した事業を創造していきます。
●商材としての看護師の活用法
①既存ビジネスに看護師(医療的技術・知識・経験)という付加価値をつける
(例)
・看護師の運行する介護タクシー
・看護師資格保持のツアーコンダクター
・看護師によるアロマテラピー
・看護師によるベビーシッター
・看護師によるレクリエーション・コーディネーター
等々
②新たな看護ビジネスを創造する
(ニーズを生む社会状況)
・少子高齢化社会
・生活習慣病をはじめとする慢性疾患の増加
・医療費の増大
・ストレス社会
・家族関係の変化
・病気治療から疾病予防・健康増進へ
・救命・延命中心の医療からQOL(クオリティ・オブ・ライフ、人生の内容・質)向上へ
医療のあり方が、病院中心、治療中心から、地域の中で寄り添う医療へシフトしていく社会情勢を踏まえて、公的サービスのニッチを埋める民間ビジネスとして、看護師を活用した事業を創造していきます。
組織(チーム)のメンバーそれぞれの役割分担を自動車に例えてみると
●エンジン
勢いをつける盛りあげる役割。自分から声をかけポジティブな言葉をかけ何にでも積極的に働きかける。楽しさと激しさの象徴で組織の動力になりきる。
●ブレーキ
勢いを止める。思考を促し事故を防ぐ委員長のような存在。理性的に判断し勢いを調整する。
●ボディ
組織をまとめる役割。事故にあう時は身を呈しドライバーを守る。見られることを意識した外見と身を守る硬さが大事。
●ドライバー
組織の司令塔。必ず一人で道を決める決定権を持つ。組織がどちらに向かうのかはドライバーの決定次第。
●ナビ、メカニック
ドライバーが行きたいところへ行くために道を選ぶ役割。エンジンなどが順調に動くようにメンテナンスや調整
を行う。
それぞれメンバーの性格・志向・得意分野にあてはめ、人数が少なければ複数の役割をあてはめてみても面白い。
個人的行動にも、このパートを意識しながら動いてみるのも有意義かも。
●エンジン
勢いをつける盛りあげる役割。自分から声をかけポジティブな言葉をかけ何にでも積極的に働きかける。楽しさと激しさの象徴で組織の動力になりきる。
●ブレーキ
勢いを止める。思考を促し事故を防ぐ委員長のような存在。理性的に判断し勢いを調整する。
●ボディ
組織をまとめる役割。事故にあう時は身を呈しドライバーを守る。見られることを意識した外見と身を守る硬さが大事。
●ドライバー
組織の司令塔。必ず一人で道を決める決定権を持つ。組織がどちらに向かうのかはドライバーの決定次第。
●ナビ、メカニック
ドライバーが行きたいところへ行くために道を選ぶ役割。エンジンなどが順調に動くようにメンテナンスや調整
を行う。
それぞれメンバーの性格・志向・得意分野にあてはめ、人数が少なければ複数の役割をあてはめてみても面白い。
個人的行動にも、このパートを意識しながら動いてみるのも有意義かも。
●成功のポイント
①起業前に苦労談や、修行経験がある
②人脈を大切にしている
③自社(自分)の強みが明確である
④情報量が多い
⑤チャレンジを楽しんでいる
⑥ビジネスは手段であり、さらに大きな目標を持っている
●起業に向けて大切なこと
①アイデア実現に向けた行動
②忍耐力
③理解者の存在
④客観的に評価されること
●起業に必要なこと
①経営知識
②資金
③支援者・アドバイザー