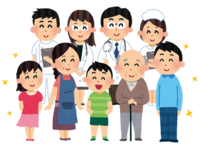老いを受け止める
お盆休みは皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は故郷の母と一泊二日のプチ旅行をしてきました。
離れて暮らしていると、一緒に過ごす時間は本当に貴重に感じられますね

こんにちは。
想いを繋ぎ 笑顔を増やす
メッセンジャーナース 鶴田恵美です。
在宅医療の現場で働いていてよく感じたのが、
老いをどう受け止めるか、ということでした。
在宅医療を受ける患者さんは、基本的に
「病院に通院できない患者」です。
ですから、高齢になり寝たきりの方も多くいました。
人は誰でも老いていきます。
そして、老衰という言葉からもわかるように、
老いて衰弱していきます。
それを自然なこととして捉えるのか、
それとも老いに抵抗し立ち向かうのか、
何がいいのかは、人それぞれの価値観により違います。
例えば、高齢の方はだんだん食も細くなってきますね。
それが長く続き、いずれ食べられなくなったらどうしますか?
食べられなくなる理由は一つではありません。
認知症で「食べる」という行為が出来なくなってしまったり、
活動量の低下で必要とするエネルギー量が少なくていいため、
体が生理的に受け付けなくなっていったりもします。
嚥下機能(物を飲み込む働き)が低下することもあります。
この場合、誤嚥(食べ物が食道ではなく、誤って気管側に入ってしまうこと)
の可能性も高まります。誤嚥性肺炎という言葉は聞いた事がありますよね。

食べる=生きる事
食べられなくなったら死ぬ
というイメージはほとんどの方にあるかと思います。
ですから、もしもあなたの大切な方が、
食べられなくなったら、「どうにかして食べさせなくては」
「食べないのであれば、点滴や胃瘻はやむを得ない」
と思われるのではないでしょうか。
しかし、自分の死に思いを巡らせた時には、
「自然な形」「延命はしない」
「鼻からチューブを入れたり胃に穴をあけたりするなんて嫌」
という言葉をよく聞きます。
「自分」のことと「大切な人」のことになると、
やはり違うのですね。
ここが、介護される側、する側の違いともいえます。
この溝はとても大きくて、
誰の想いに沿っていくのかが難しいところでもあります。
認知症を発症していて意思疎通ができなくなっていれば、
介護者が意思決定をしていかなければなりません。
認知症で今更確認できないけれど、
母はいったいどうしたいのかしら・・
もし話ができるとしたら何を選択するかしら・・
先日105歳で亡くなられた日野原重明医師はご自分の意思で
胃瘻も選択しなかったと報道がありましたね。
・・・
長くなってしまったので、
次回に引き継いで、
実際に在宅の現場で出会った患者さんとご家族の、
「食べる」ことのエピソードをお伝えしていくこととします